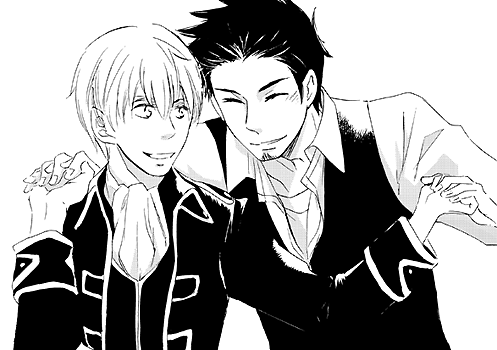靴を履くために座り込んだ玄関先、開けっ放しの扉から人の入ってくる気配がある。
近藤は、顔を上げることもなく無防備に靴と格闘を続けた。
スッと手元に影が差し、入ってきた人物が正面に立ったことがわかる。
「おじょーさん、お手をどうぞ」
ここでやっときょとんとした表情の顔があがった。
「おじょ……?」
近藤の正面には、沖田が立っていた。
声でわかっていたから、それには驚かない。
「どーしたの総悟、新しい遊びかなんか?」
不可解な呼びかけの理由を求める質問は、軽く睨むような視線だけで流された。
「あれは忘れもしねえ、昨日の朝」
「え?うん、昨日の朝だからね?」
「近藤さんアンタ、靴はいて立ち上がるとき、どっこいしょって言ったんですぜ」
「え?言った?」
「言いやした、忘れもしねえ」
そこでなんで沖田が苦虫を噛み潰したような表情なのか、近藤には分からない。
「どっこいしょ対策でさぁ」
話の流れを理解するのに時間がかかる。
「でも年寄り扱いはしたくなかったんで」
一拍おいて近藤が頷いた。
「ああ、それでおじょーさん?」
気の遣い方間違ってるよ、そんな一言がどこか満足げな沖田を前にすると口に出せなかった。
なんだかんだ言って近藤は沖田に甘い。
「ふーん、歳かなー」
「歳じゃねえ!!」
思ってもみないところで強い反発が返ってきて、近藤は面食らう。
「え」
「近藤さんと俺だってそんなに変わんないでしょ」
「いや、そりゃあ変わるだろ、そこまで図々しくはな……」
キッと睨まれ、近藤は言葉と笑いを引っ込めた。
この様子は何か気に入らないことがあるのだろう、近藤はすぐには思い至らない原因を探すために、いまのやりとりを思い返した。
「総悟は俺がおじさんなのがイヤなの?」
「んなわけないでしょう、近藤さんがおじさんでもおじいさんでもおばさんになっても愛してますぜ」
「いや、おばさんにはならないけどね」
あたりをつけた答えを速攻で否定され再考を余儀なくされる。が、他の答えなど見つからない。
「じゃあ何が気に入らないんだろうね、この子は」
近藤がお手上げだと呟けば、さらに一層強く睨まれた。
口の達者な沖田が憎まれ口も叩かなくなるというのは、昔から本当に機嫌の悪い証拠だった。
(こりゃ相当虫の居所が悪い)
近藤は、何が原因なのかもう一度考え直してみる。
睨まれるのだってこの短い間に三度目だ。
(ん?三度?)
三度睨まれたときの状況をもう一度思い返す。
(ああ、そうか)
おそらくこれが正解だろう。
「総悟、手ぇ貸して」
靴はとっくに履き終えた。
近藤は座ったまま、沖田に手を差し出す。
途端、沖田は表情を緩め、恭しく大げさに一礼してみせた。
まるで舞踏会に招かれた貴族のように。
沖田はもともと目を引く整った容姿をしているから、そういう所作が恐ろしく様になる。
差し出した近藤の手を沖田は下から掬うように、柔らかく絡め取る。
近藤は堪えきれず、噴き出した。
「ぶはっ!そーご!王子様みたいだぞ」
沖田は、笑われても気を悪くするでもなく、ふふん、と不敵に笑う。
「一曲、お付き合いくださいますか?」
「あははははは!踊るの?いーよ!」
近藤も沖田もダンスなんて知らない。
それでも近藤は、二人で踊るところを想像してみた。
それはきっと、ものすごく楽しいに違いない。
ぐっと握り込まれた手に力が入り、沖田に引き寄せられるように近藤は立ち上がる。
「ありがとな、総悟」
いつからか、沖田は近藤に子供扱いされることをひどく嫌った。
近藤としてはそんなつもりはなかったのだが、確かに思い返せば、そう取られても仕方ない言動をしていたことに気付いた。
つい、可愛くて、無意識に。
いつの間にか、繋いだ手だってこんなに大きくなっている。
いつまでも子供じゃない、近藤は、そんな当然のことにほんの少しの淋しさを自覚した。
その淋しさがどんな感情に基づいているのかということには気付けなかった。
ただ、チクリとした棘のような痛みを笑ってごまかす。
「よし、見回り行くか」
「へい」
近藤の手を離さないまま、沖田が歩き始める。
その手の温かさにわだかまった棘がぽろりと抜けたような気がして、少し迷った間に近藤は手を取り戻すタイミングを逸してしまった。
(まあいいか)
こんなことも今のうちだけだろう。
近藤は、思春期の娘を持つ父親のような心境を地でいく。
さっきの淋しさも痛みもきっとそのせいだろうと、そう結論づけた。
2007-12-30
冬コミペーパー再録
(どん+はわいさん合作絵↓が元ネタです)